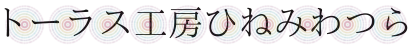『おかわかめ』の詳細
おかわかめを楽しむ:栄養・調理法・保存のまとめ
おかわかめは「雲南百薬」とも呼ばれるつる性の多年草で、葉に厚みと粘りがあるのが特徴です。生のままは少し青い香りがありますが、軽く茹でるとクセがなくなり、細かく刻むとぬめりが出て海藻のような食感になります。茹でた姿がわかめに似ていることから「おかわかめ」と呼ばれ、市場ではまだ珍しいものの家庭菜園でも育てやすい野菜として広まりつつあります。
おかわかめの旬と産地
おかわかめの収穫時期は主に6月〜10月で、気温が下がる冬は地下の塊根で休眠し、春になると再び芽を出します。国内では大分県中津市の栽培が盛んで、暖かい地域で育ちやすいほか、北海道の伊達市でも生産されています。
家庭でもプランターで育てられるため、緑のカーテンとして利用する方も増えています。日当たりの良い場所で育てると、夏の日差しを和らげながら収穫も楽しめます。
主な栄養素
おかわかめは「百薬」という別名のとおり栄養価が高く、ミネラルやビタミンを豊富に含んでいます。主な含有量(100 gあたり)は次のとおりです。
| 栄養素 | 含有量 | 役割 |
|---|---|---|
| マグネシウム | 約62.3 mg | エネルギー代謝、骨と歯の柔軟性を支えます。 |
| カルシウム | 約70.8 mg | 骨や歯の形成を助けます。マグネシウムとバランスよく摂ることで骨粗しょう症予防に役立ちます。 |
| 亜鉛 | 約0.709 mg | 細胞の再生や美肌を支え、味覚の維持にも関わります。 |
| 葉酸 | 約24 µg | 血液の生成を助け、肌や髪の健康を守ります。 |
| β‑カロテン | 約8,400 µg | 抗酸化作用があり、粘膜や免疫機能をサポートします。 |
| ビタミンA | 約1,740 µg | 目や粘膜の健康維持、眼精疲労の回復に役立ちます。 |
これらのミネラルやビタミンがバランスよく含まれているため、代謝アップや美肌、骨の健康、免疫力のサポートなど幅広い働きが期待できます。
おいしい食べ方
おかわかめはさっと茹でると食べやすくなり、刻むことで粘りが出てわかめのような口当たりになります。簡単な調理例をいくつかご紹介します。
-
お浸しや和え物
沸騰した湯に10〜20秒くぐらせ、冷水に取って水気を切ります。そのままポン酢やしょうゆでシンプルにいただくと粘りと歯ごたえが楽しめます。 -
サラダ
熱湯を通して冷やした葉を他の野菜と混ぜ、ゴマ油+塩やポン酢などと合わせると海藻サラダのような食感に。 -
天ぷらや炒め物
生の葉に衣を付けてカラッと揚げたり、一口大に切って炒め物に加えるのもおすすめです。 -
味噌汁やスープ
仕上げにちぎったおかわかめを加えると緑が鮮やかに残り、粘りが溶け出して喉ごしが良くなります。
粘りの正体はムチンと呼ばれる多糖類で、オクラやモロヘイヤにも含まれる成分です。胃腸や喉をやさしく潤す作用があり、夏の疲れを癒やす野菜として親しまれています。
保存方法と選び方
新鮮なおかわかめの見分け方:濃い緑色でハリがあり、厚みのある葉を選びましょう。
乾燥に弱いので、購入したら湿らせたキッチンペーパーではさんで保存容器やポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保管しましょう。
保存期間:
- 冷蔵保存:約2週間
- 冷凍保存:約1カ月
茹でてから凍らせると粘りが失われるので、生のまま冷凍するのが適しています。家庭菜園で収穫した場合は、すぐに使い切れないときに小分けにして冷凍しておくと便利です。
おわりに
おかわかめは暑い季節に旬を迎え、豊富な栄養素と独特の粘りで体と心をやさしく整えてくれる野菜です。さっと茹でてお浸しや味噌汁に、衣を付けて天ぷらにと調理法も豊富で、家庭でも気軽に栽培できます。見えないエネルギーを整えることを探求する私たちにとって、おかわかめは自然のリズムと調和を感じさせてくれる一品です。日々の食卓に取り入れて、身体の感覚や呼吸、集中力にどんな変化があるかぜひ確かめてみてください。